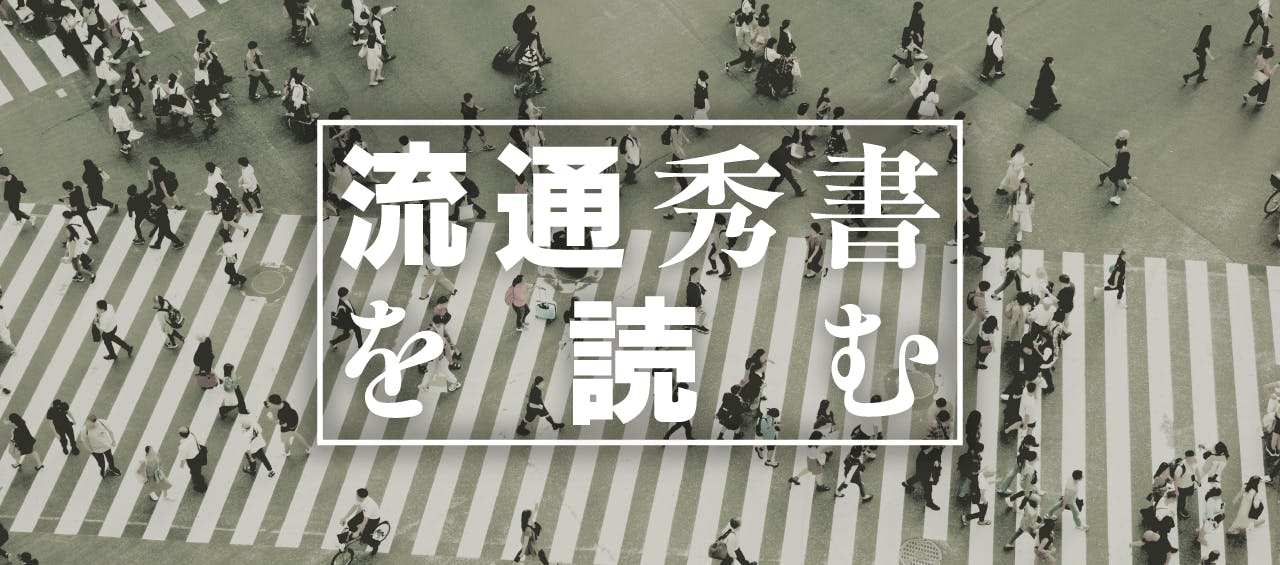流通秀書 第3回『オリオン堂繁昌記』
「流通秀書」とは、1993年4月1日号から1997年9月15日号まで、ダイヤモンド・チェーンストア誌の前身である「チェーンストアエイジ」誌で連載された企画である。吉田貞雄氏(故人)による連載は当時、多くの読者に愛された人気連載であった。流通革命前夜、もしくは真っ只中に書かれたこれらの秀書を読み解いた記録から、業界が進んだ道と変わらぬ課題を学び直します。(本文の肩書、年度などは連載当時のまま)」
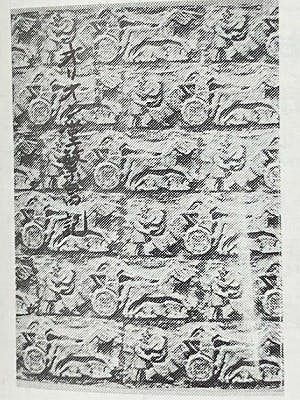
喜多村実・著
顧客第一主義の実践事例を貫く
1981年4月、大手チェーンストアの新入社員合同研修会に一人の老人が壇上にのぼった。「私は初めてこの会社におじゃまし、現在の社長にお目にかかったとき、店はたったの17坪でした。昭和32年の9月のことです。〈中略〉この小さな店がどうして大きくなったのか、実は共通の要素があります。顧客第一主義を貫いた点です」
3年後、この人は80歳で黄泉(よみ)の国へ旅だった。17坪の社長だった男は、師の通夜に真っ先に駆けつけ、4時間以上にわたって冥福を祈った。老人の名は、公開経営指導協会理事・喜多村実氏。17坪の社長は中内功氏である。
喜多村実は、ワナメーカーの自伝に心を打たれ商いに開眼。1923年10月、東京・目黒に「オリオン堂洋品店」を開業。そのユニークな商法に戦前から清水正己、倉本長治(雑誌『商業界』創業者)、岡田徹、上野陽一氏らコンサルタントから模範繁盛店として全国に喧伝された。
1949年、喜多村氏は中小小売店の指導機関を設立するや、その指導は全国の小売店から圧倒的な支持を得た。「オリオン堂洋品店」の経営に着目した産能大創始者・上野陽一氏は、仏教を通じてつかんだ人材教育の神髄を次のように披瀝(ひれき)している。
「釈迦の時代には、サンガという単位があった。サンガは僧という字が出たもとだ。サンガの単位は、大体、4人から20人ぐらいまでだった。僧4人のうち1人が先輩格に当たるもので他の3人が先輩の教えを聞くということが行われていた。当時から多くて20人、それ以上になると分家して、もう一つのサンガをつくるといった具合にやってきたようだ。こうしたやり方は、本当に教えを伝えようとした場合には、何十人という集団になったのでは、かえって焦点がぼやけるのだ」
そのサンガ方式を行って、チェーンストアの仲間入りをしようと考えている一団が喜多村実氏のコーチを受けた。
和田源三郎(イズミヤ創業者)、西端行雄(ハトヤ店主・のちニチイ創業者)、小林敏峯(ヤマト小林店主・現ニチイ社長)、岡本常男(赤のれん店主・のちニチイ取締役)、福田博之(富久屋社主・のちニチイ取締役)氏ら5人の商人たちは、戦前に発行された『商店経営』(編集長・岡田徹)に5年間連載された喜多村実氏の実践商戦記『オリオン堂繁昌記』を復刊させた。1962年のことである。編集後記に、小林敏峯氏の記述がある。
「先生の本棚を、荒らせているうちに本書の原本を発見し、先生のお許しを受ける前に強引に印刷・発行した」と。しかし、この本は発行されるや、たちまち当時のチェーンストア創業者たちのバイブルとなった。
なぜか。実はこの書は実践を通じ、1つの店舗をどのように発展させることができるのか。そのノウハウが書かれていたのである。
「優秀な販売員は、また優秀な応用心理学者である」(29ページ)、「昭和4年に行人坂に店を移転しましたが、そのときは店全体を珍しい包装紙の図案で塗りつぶし、店全体を広告塔に仕上げました」(42ページ)、「商いの秘訣は、天の時、地の利、人の和の融合である」(56ページ)、「小売店繁栄の秘訣は、その土地に最も適合したその商品を、その土地に最も適合した販売方法で売ることです」(55ページ)、「店員を見れば主人の性格がわかる。店を肥やさんと欲せば、まずその店員を肥やせ!」(166ページ)、「商品を売ると思うな、その価値を売れ」(131ページ)。
いずれも、喜多村実氏の65年前の言葉である。1963年、彼は小売業者の協業化を示唆し、指導に当たった。その機関は日本衣料協同研究所と称され、その略称「日衣」が、現在の「ニチイ」の原形であったといわれている。
彼はその生涯を中小商店のために捧げた。その武器は一店舗の「繁昌店」理論であった。価格を武器に店舗そのものを1ユニットと考え、高速回転論でもって、次代に飛躍するために資本を獲得する「成長店」の理論は、渥美俊一氏の登場まで待たねばならない。
購入について
※取り扱いが終わった製品もございます。