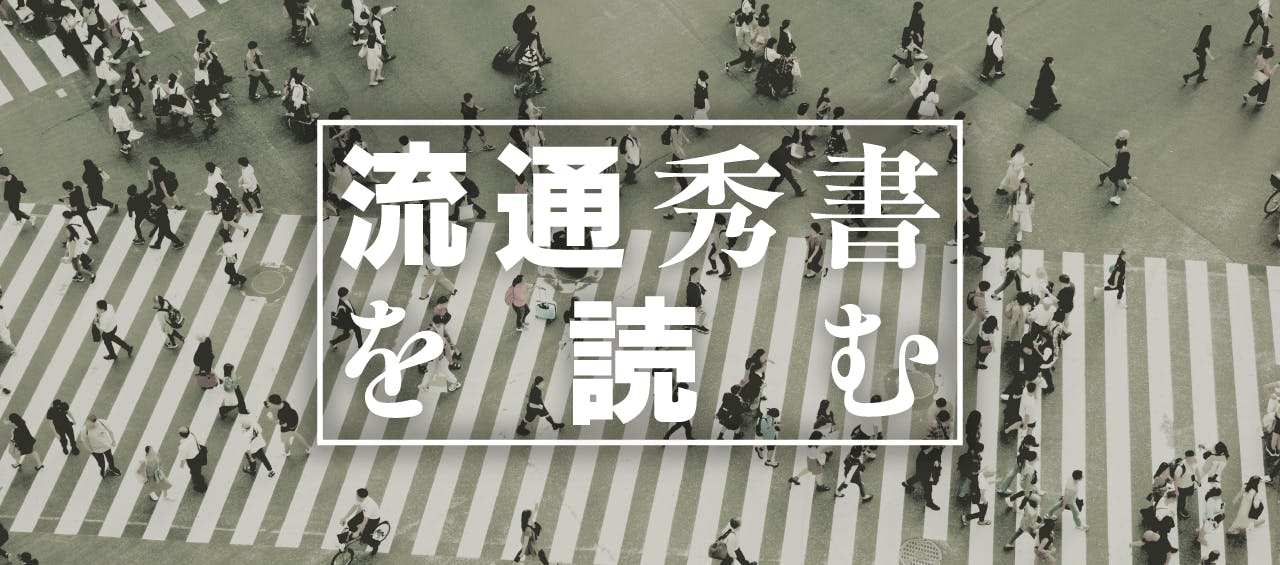流通秀書 第4回『小林一三翁に教えられるもの』
「流通秀書」とは、1993年4月1日号から1997年9月15日号まで、ダイヤモンド・チェーンストア誌の前身である「チェーンストアエイジ」誌で連載された企画である。吉田貞雄氏(故人)による連載は当時、多くの読者に愛された人気連載であった。流通革命前夜、もしくは真っ只中に書かれたこれらの秀書を読み解いた記録から、業界が進んだ道と変わらぬ課題を学び直します。(本文の肩書、年度などは連載当時のまま)」
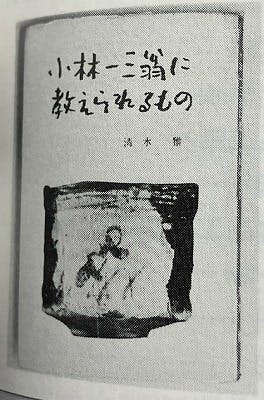
(1957年発行)
清水 雅著
好奇心・研究心・探求心の三心精神
小林一三の人材感
人間はいくつかの宿命を必然的に負う存在である。ある時代に生まれ、いくつかの時代を通過して別の時代に死んでいく。この国に生まれ、この文化にはぐくまれ、いくばくかの文化的貢献をなして死ぬ。
これらが人間の負う宿命というものである。だれも宿命を避けて生きることはできない。拒否できないものの、最たる存在が人間である。妥協か同調か、あるいは協調か、抵抗・反抗そして挑戦か、これらのファクターによって人は宿命と共存して、運命を切り拓(ひら)き立命(りつめい)を得て、命数を知る。
1957年1月26日、『ニューヨークタイムズ』に一人の男の訃報が掲載された。その一部は、こうであった。
「--彼は1907年、一電鉄の経営に参画し、数年後、大阪から宝塚まで30マイルの路線を運行するこの会社のヘッドとなった。営業拡大のため、彼は宝塚を音楽ホールに転換しようと決意し、近郊の家庭の娘たちを募って、雪・月・花そして星と呼ばれる4つの組みに編入し、音楽とバレエを教えた」
彼とは、阪急電鉄を創設させた小林一三のことである。
小林一三は、1957年1月25日、84歳で逝(い)った。
同年7月3日、愛弟子(まなでし)、清水雅氏(のち東宝グループ社長)の、この本が発行されるや、たちまちベストセラーとなった。もちろん、チェーンストアの創業者たちも、ひそかにこの書の読者となって、小林一三に憧(あこが)れ、チェーンストアという仕組みを超えたとき、彼のような事業センスにロマンを抱いたのである。この本の著者、清水雅氏が小林一三に学んだもの――人材について、小林氏は弟子に語っている個所がある。
「――私は陰険な人が大嫌いだ。出来なくても誠実にやっている人は、指導をして行くと、だんだんよくなって来て、おそいながらも、とにかく出来るようになって来る。陰険な人は賢いように見えても、色々とやっている間に、とかく問題を起し勝ちである。誰やらがどうやらしてなどと、人の心持を陰で乱(みだ)して来るために波風が起る。私はそれが大嫌いである」(78ページ)。
なにやら、時空を超えて現下の流通マンにネアカであれと、言っているようではないか。
小林一三は、83歳まで常に現場を見て回った
プライベートブランドも開発
「――〈小林一三翁は〉決してマンネリズムにおちいらないよう、研究々々と進んで行かれるのであるから、周囲にいるものはじっとしていられない。
気に入ったイスなどがあると、他人様の応接室でも、ちょっと失礼といって、イスの裏をひっくり返して、ウラの構造などしらべられたという話しを聞いたが、私の先輩などお座敷テンプラを食べに行って、勘定を払って出て来ると、今のエビの値段は、一匹いくらだという質問にぶつかって、返答に困っていると、聞いてきたまえ、とあびせられて、あわててテンプラ屋のおやじに聞きに行ったら、今度はおやじの方が面くらった、というような話しを聞かされたほど、研究心が強かったのである」(25ページ)。
「――ちょっとついて来給え、ものの見方というものはこういうようにするものだと、忘れもしない、五階の売場へつれて行かれてあの柱からこの柱までおよそ五、六十坪ぐらいの売場の中で、どこに欠点があるかさがして見給え」と言われ、悪い個所を10ヵ所も指摘された、とも記されている。また、牛の飼育事業も、戦前小林はビジネスとして手がけており、そのピークは「一時八千五百頭に及んだ」(55ページ)し、さらにプライベートブランドとして、ライスの「宝米」を発売していた、という。
子供のような好奇心・研究心・探求心を、小林一三は「一の先見力をつけるには、三心が必要」と述べ、当時のチェーンストアの創業者たちにとっていかなる理論書にもまさる魅力的な書であったに違いない。
購入について
※取り扱いが終わった製品もございます。